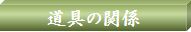| 年代 | 主な遺跡 | 特徴 |
|---|---|---|
| 草創期 BC12000〜 | - | 縄の文様はなく、木や貝などの物をおしつけた文様。 |
| 早期 BC9000〜 | 長七谷地遺跡 田面木平遺跡 | 縄の文様がつけられはじめる。 貝を押し当てた文様もある。 |
| 前期 BC6000〜 | 蟹沢遺跡 | 平らな底がつくようになる。 |
| 中期 BC5000〜 | 松ヶ崎遺跡 | ひも状の飾りをつけたりするようになる。 |
| 後期 BC4000〜 | 町畑遺跡 | 椀・皿・きゅうす型など、 様々な形の土器が作られるようになる。 大量生産された、同じ形の土器も出土。 |
| 晩期 BC3000〜 | 八幡遺跡 | 形の種類が多く、 きれいな文様がつけられるようになる。 漆を塗った赤色の土器も出土。 |